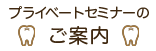2024年6月1日東京ミッドタウンホールにて日本顕微鏡歯科学会シンポジウムの座長を務めました。
今回は実行委員長も兼務していたので筆舌に尽くし難い激務でしたが、どうしても20回記念となる学術大会の場で「見る」について考察したい一念から自らを奮い立たせました。
顕微鏡を使う歯科医療従事者は全員、顕微鏡は見えるから素晴らしいと言います。
しかし、顕微鏡を使用しただけでは死角は絶対に見えません。
口腔内にミラーを入れない限り死角は見えないのです。
しかし同じ顕微鏡を使用しても片方では見える、もう片方ではそれは見えていないだろうという噛み合わない会話が延々と行われ、影響力のある直視主体派の歯科医師は直視でなんら問題ないとSNSで発信し、それに同調する歯科医師が多数います。
ミラーを主体とする歯科医師は少数派のようです。
両者の「見える」とは果たして同じことを意味しているのだろうかと長い間疑問でした。
20周年の記念大会で顕微鏡歯科治療の根源となる「見る」について正式に学会という場でディスカッションをしたいという強い思いから、今回実現することができました。
直視主体とミラー主体の優劣をつけるのではなく、どうしてこの認識の違いが起こるのかその真理に少しでも近づくために、今回は文化史の視点から名古屋大学名誉教授の鈴木繁夫先生に詳細に論じていただきました。
直視主体の歯科医師とミラー主体の歯科医師のこの3人でシンポジウムを行いました。
タイトルは
Microscopic Dentistryから顕微鏡歯科への道〜「見る」西洋の視点と和の視座〜
去年の9月から約10か月鈴木先生とミーティングを行い、後半3ヶ月はシンポジスト3人と私の4人でミーティングを行いました。
鈴木先生は歯科医療の知識0出発でしたがその実直さと勤勉さでかなりの量の資料を読み込み、最終的には顕微鏡歯科治療の本質まで鋭く斬り込んできました。
鈴木先生との出会いは「死角を見る視覚ー日常思考はどこまで信じられるかー」が全ての始まりでした。
15世紀フィレンツェ司教座聖堂(ドゥオーモ)正面の洗礼堂につけるレリーフの公開コンクールでギベルティとブルネレスキの一騎討ちの末ギベルティのレリーフが勝利したことから始まる論文は、私の知的好奇心をすこぶる興奮させました。
線遠近法とリリェーヴォという両眼・視点移動の遠近法の制作法の違いを解説しており、ルネッサンス以来の私たちが見慣れている線遠近法的な見方の落とし穴、つまり確定断言という日常思考について触れ、マグリットの絵画を例に解説しています。
続いて鈴木先生の著書である「フーコーの投機体験」を読みましたが超難解レベルでした。
今まで触れたことがない分野のことを鈴木先生から沢山、楽しく教えていただきました。
カント、ドゥルーズ、フーコーなどの難解な哲学者の本、レナルド・ダ・ビンチの鏡文字、サピア=ウォーフの仮説、逆さ眼鏡の研究、鏡映反転、能動態・中動態など、歯科の分野でない資料もたくさん読みました。
認識や認知は言語や文化が強く影響するというサピア=ウォーフの仮説は最早仮説ではなく定説で、ある言語を使う国でしか使われていない言葉があります。
。
鈴木先生のブログでは日本語と英語を対比させ、日本語はモバイルカメラ型、英語はスタジオカメラ型の言語であることが書かれています。
屏風絵で描かれている合戦の絵などは日本独特のモバイルカメラ型です。
川端康成の”トンネルを抜けるとそこは雪国だった”という文章を読んで思い浮かべる情景も日本語圏と英語圏の人達では異なります。
11月頃には言語、すなわち能動態・受動態と能動態・中動態の観点から見える認識の違いを考察しました。
中動態とは聞きなれない言葉ですが、インド・ヨーロッパ語にはこの中動態というものがあったようです。
現在は能動態と受動態の対立ですが、昔は能動態と中動態の対立でした。
中動態の中に受動態が含まれていたのですが、いつしか受動態が台頭してきました。
理由は色々考えられますが、意志と責任を明確にする便利なものなので現在では能動態・受動態の形になったようです。
*言語学者の小島剛一先生による厳密な正しい能動態・受動態と能動態・中動態とは異なるようです。
この視点ではミラー主体が能動態・中動態で直視主体は能動態・受動態の体をとっていますが、コミュニティの中で自己表現しようとすると、自由意志の有無が問題になる能動態・受動態の枠にはまってしまいます。だから「見る・見える」という同じ言葉を使っていても言葉の意味するものが異なるようになります。
鈴木先生とのディスカッションを進めるうちに、文化的な視点から考察した方がシンポジウムはわかりやすくなるんじゃないか、ということで「見える」という言葉をめぐる意匠について解説してくださることになりました。
文化的意匠から直視派は真景、ミラー派は実景を見ていることを説明し、認知的意匠では立体構築について絵画と和絵、縦横奥行きの比率を使って説明していただきました。
どうやら日本人が持っている和的感性は正確な立体感覚を掴むのに不利らしいです。
年が明けて4人でのディスカッションを何回か経たある折に、鈴木先生はミラーテクニックができる能力はある意味ギフトだ。それくらい難しいことです。と私に話してくれました。
私は今までミラーテクニックを習得できない人はただ単に努力不足で、「見る」という意味を軽視している人なんだな、と思っている部分はありました。
そう言われるとこれだけミラーテクニックが普及しない理由もわかる気がします。
一方、歯科大学の卒業したばかりの若い歯科医師にミラーテクニックを教えると、臨床経験がないほど飲み込みが早いのも経験しています。
先生によると自転車や水泳は大人になって初めてやっても習得が難しいことは研究で明らかになっており、特に一輪車は小学4年生頃までに習得しないと一輪車特有のバランス感覚は得られないこともはっきりわかっているそうです。
もちろん若い歯科医師個々のバックグラウンドも影響がありますが、できるだけ早い段階でミラーテクニックを習得させたいです。
シンポジストの三橋純先生は、本当の「見える」を知るにはミラーテクニックを習得しないとわからないんだよね。ミラーテクニックを習得した人で直視主体ですと言っている人は今までいない、と。
これを聞いて私は、これって死んでみないと死後の世界がわからないというのと同じですよねと笑っていました。
シンポジウムにおいてもミラーでも直視でもどっちでも良いという意見が出ましたし、過去にもそのように意見する歯科医師は沢山いました。
こんな事を言えるのは直視もミラーテクニックもできる人しか言えない事なのに、これが罷り通っている歯科医療の現状に寂しさ、物足りなさを感じました。
医科は早々に死角に対して顕微鏡と内視鏡を組み合わせたハイブリッド法を行っています。
三橋先生から面白い話をお聞きしたのですが、ある医科大学の消化器外科の先生方にミラーテクニック主体の顕微鏡歯科治療について講演した際、そこの教授がたいそう驚いてどうやってミラーテクニックを習得したのかと質問があったそうです。
かつて内視鏡はまだまだ径が太く口からカメラ、肛門から処置する器具を入れたそうです。
まさにミラーテクニック的な処置になるため、難しすぎて断念した経緯があるそうです。
現在は内視鏡はかなり進化しているのでそのようなことはありません。
彼らはミラーテクニック的な方法は諦めたが違う方法を編み出し、道具としての内視鏡を現在の形にしました。
これは直視でもミラーでもどっちでもいいじゃん、的な能天気なことで思考を止めていません。
正確に見えるとはどういうことなのかを認識しているからミラーテクニックに変わるものを開発したのです。
だから、どっちでもいいじゃんという考えは顕微鏡歯科治療の発展を妨害する考え方なのです。
どうして歯科はまだこのレベルなのか。
多分命と直接関わりがないので甘いんです。
隣の歯を削ろうが見落としがあろうが死ぬわけではないので崖っぷちに立たされていないのです。
4人でのディスカッションをしていて私が興味を引いたのが、直視派のシンポジストの先生の「見る」意識が回数を経るごとに変化してきたのではと感じました。
もちろんミラーを使わない直視なのですが、明らかに過去の動画と比べても意識の変化があったと私は感じました。
どうしてそんなに「見る」に執着しているのかといえば、「見る」を全員で正しく認識できれば新しい治療法や器具の開発など顕微鏡歯科治療の将来を良い方向に進めるかもしれないからです。
鈴木先生によるとミラーテクニックは写実的で独自の立体感覚を持っているそうです。
暗黙知という言葉がありますが、どのように行っているのか説明できない事を言うそうです。
例えばどうやって自転車に乗るかなど。
確かに技術的な暗黙知はあることは確かです。
技術的なことではなく「見る」「見える」とはどういうことなのかの認識のズレが大きいのかなと感じています。
この暗黙知をギフトを持っている人と臨床経験の無い、もしくは少ない歯科医師に届けられるように活動したいです。
どこかの歯科大学・歯学部が私を研修医などの教育係として雇ってくれないかな。
今現在自分なりにまとめると、理論的にも現実的にも真の意味での「見る」治療はミラーテクニックを主体としないと実現できない。
「見る・見える」の認識を変えることは難しいことなのかもしれないが、真景とか実景とか甘っちょろいことをいっている限り統一されない。
言い換えれば歯科は真景・実景と言っている余地があるくらい歯科は甘い治療だということ。
このことが見えるという認識の妨げになっているのではないかと考えている。
ミラーテクニックを習得するのは相当の修練が必要になる。
そもそも顕微鏡歯科治療と従来の肉眼治療の治療結果の差にエビデンスはない。
直視主体とミラー主体の各顕微鏡歯科治療の間に差があるエビデンスはあろうはずがない。
医科の例を挙げれば、「見る・見える」認識さえ多数の人が正しく認識できればそれに変わる方法を開発できる可能性がある。
エビデンスを軽視するわけではないが、私たちはコロナウィルスでもエビデンスという言葉に振り回されました。
現在世界中で行われているインプラント治療も30年前は骨と歯肉を貫通している棘で、そんな治療はもってのほかだと病理学者は言っていました。
まとまりのない文章になってしまいましたが、今や顕微鏡を所有している歯科医院は珍しくありません。
色々な異なる考えを持つことを否定はしないし尊重します。
ただ自然科学の中の歯科医療なので建設的な議論というものを、しがらみなどを抜きにして今後もやっていきたい気持ちを強く持っています。
おもて歯科医院
歯学博士
表 茂稔