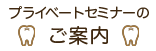2024
7/24
歯を残すための親知らず抜歯
- 2024.07.24
- ブログ歯記
- 親知らず・ 顕微鏡歯科治療(マイクロスコープ)
皆さんには親知らずはありますか?
親知らずを抜いたことがある知人から、もの凄く腫れたとか凄く痛かったなど聞いたことがあるかもしれません。
術中は局所麻酔をしているので処置をしている間は痛みはありませんが、術後の麻酔が切れた後の痛みが強いのだと思います。
私が昔アルバイトに行っていた人気の歯医者では、親知らずはリスクは高いし処置費用も安いし術後の痛みや腫れが出ることが多いので、患者さんから悪い評判がたつから全部歯科大学へ送ってね、と言われて、患者さんから見る良い歯医者と私が考える良い歯科医師のギャップは大きいのだなとなんとなく長い間抱えていました。
当院に通院している患者さんの中には、親知らずはあるけど今症状がないなら様子を見ましょうと過去に説明を受けた患者さんも多くいます。
全ての親知らずというわけではありませんが、そのほとんどは抜歯の対象になると考えています。
簡単にいうときちんと管理できる親知らずであれば残しても良いのではと思います。
完全に骨の中に埋まっていれば良いのですが、一部骨から出ていてその上に歯肉が被っている状態は良い状態ではありません。
歯肉のバリヤーは弱いものです。
抜いてしまう親知らずは虫歯になろうが何になろうが抜いてしまうので抜歯を先送りしても良いのかもしれません。
しかしその手前の歯には相当のダメージを受けるかもしれません。
そのうちの一つは虫歯です。
患者さんの一生のうちでいつ親知らずが具合が悪くなるのか予想はできません。
もしかしたら寿命が尽きるまで何事もないかもしれないし、高齢になって様々な病気を抱えた時に親知らずの具合が悪くなることがあるのかもしれません。
隣の歯のダメージもどれくらいになっているのかもわかりません。
私はなるべく元気なうちに、隣の歯のダメージがないうちに、隣の歯のために親知らずを抜歯することをお勧めしています。
当院の親知らずは顕微鏡による抜歯で、基本的に自由診療です。
動画の抜歯治療費は約9万円です。
さて、私の主観ですが、抜歯などを行う外科的な処置をする科を口腔外科と言いますが、優秀な口腔外科医の条件とは短時間で処置を終了することをいうのだそうです。
私がある新聞社の診療所の勤務医だった頃、親知らず抜歯は大学から口腔外科の先生が週1回いらして処置をしていました。
抜歯後の不快症状があった場合勤務医の私が対応するのですが、長い人で3ヶ月くら苦しんでいた人もいましたし、1ヶ月痛みに苦しんでいた人も多々いました。
なぜでしょう?
私の主観です。
優秀な口腔外科医は短時間で処置を済ますために頬側の骨をざっくり削る傾向にあります。
このほうが処置時間の短縮につながります。
処置時間が短いと患者の負担が軽くなるという考えからのようです。
骨を削るということはどうしても術後の腫れや痛みが長引く傾向があると思いますが、専門外の私にはよくわかりません。
私は、この頬側の骨を極力削らないように抜歯をしています。
私には顕微鏡がないとできません。
頬側の骨を削らない理由として術後の不快症状をなるべく出さないように、ということはもちろんですが、上述したように前隣の歯を守るための良い環境になるように頬側の骨を削らないのです。
抜歯後、穴に血液が溜まって骨が再生されます。
コップの縁の一部が欠けていたら、水は欠けたところまでしか溜まりません。
頬側の骨を削ったら血液はどこまで溜まるでしょうか?
例え舌側の骨の縁が高いところまであっても頬側の骨の縁が低ければ血液はそこまでしか溜まりません。
そうなると隣の歯の歯根の後ろ側の骨と歯肉はガクッと下がってしまいます。
こうなってしまっても一生問題を起こさない人もいるでしょう。
問題になってしまう人もいるでしょう。
ちなみにインプラントの処置をする時は骨の量、幅や高さが大事で、それが足りない時は骨造成をします。
その時にも骨の縁の高さを減らさず、なるべく高い壁を作ることが重要だという事が言われています。
しかし、なぜか親知らずの場合は躊躇いもなく頬側の骨を削ります。
何故なのか?
理屈は上述したようにわかっているはずです。
多分、顕微鏡によるミラーテクニック主体の方法ができないことが理由の一つに挙げられると思います。
今回の患者さんは残念ながら術後は無痛というわけではありませんでした。
2週間くらい痛かったようです。
親知らずが周囲へ及ぼす悪影響の将来的予測はなかなか難しいです。
外科的な処置は誰にとっても嫌なものです。
でも抜歯という困難なハードルを飛び越えられるよう、保存すべき歯の環境を整えることが大事なことだということはこれからも患者さんに伝えていきます。
自分が処置した患者さんが腫れたとか痛いとか訴えるのを目にするのは、できれば避けたいことではありますがこの処置をすることが本人のためになるのなら、という思いです。
今までの患者さんのほとんどは術後の腫れや痛みは無いか軽度でしたが、どのような状態であってもなるべく負担が軽くなるように技術の向上に務めたいです。